兵庫県警は9日、「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました。警察によりますと、立花容疑者は、竹内英明元兵庫県議の名誉を毀損したとの疑いで逮捕に踏み切ったようです。既に亡くなっている故人に向けての名誉棄損罪ということで、珍しいケースのようですが亡くなった人を冒涜する行為と聞くと穏やかではないですね・・・。
そこで本記事では、名誉毀損罪について調べてみようと思います。
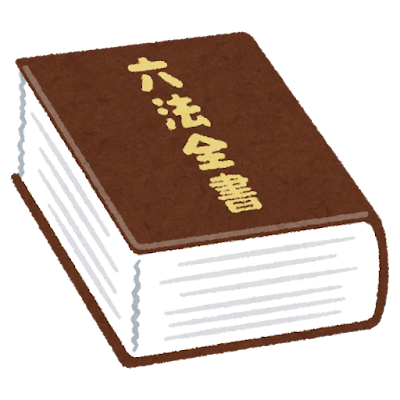

名誉毀損罪の構成要件(成立要件)
名誉毀損罪は刑法230条に規定されています。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元―刑法|条文|法令リード
公然性
名誉毀損罪の構成要件の1つ目は公然性です。刑法230条の条文にもある「公然と」とは、多数の者が認識できる状態又は不特定多数の者が認識できる状態という意味です。この判断基準は少しややこしいのですが、「他人に伝わる可能性があるかどうか」がポイントになります。実際に伝播しているかどうかは関係なく、伝わる可能性がある場所で行えばアウトです。
不特定又は多数の者が使用する建物、公園、電車・バス内、駅の構内などの公共の施設・場所は「公共と」に該当する典型例であると言えますが、「少人数での噂」もアウトです。広がる可能性があるというだけで成立します。
他にはSNS等を通じてインターネット上に情報を拡散することも該当します。現実に誰かに閲覧されていることや見られていることは必要なく、その可能性さえあれば該当します。アクセス数が少ないこと、アカウント鍵付きであることは公然性を否定する理由にはなりません。他方で、自宅内や一対一の電話やメールなどおよそ他人の目の届かない場所、空間は該当しません。
事実の適示
「事実を摘示し」とは、人の社会的評価を低下させるおそれがある具体的事実を指摘、表示することです。今回の例だと、
「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。警察の取調べを受けているのは多分間違いない」
引用元―2024年12月大阪府泉大津市長選挙の街頭演説より
のようになります。竹内議員が警察の取り調べを受けているかのように事実を適示しています。実際にはそんな事実はなく、嘘を言っていたようですが、具体的事実であれば真偽を問わず成立しますので立花氏の発言は「事実の適示」としてはアウトです。
さらにそれが事実であったとしても、人の社会的評価を低下させる内容であれば「事実」を摘示したことにあたります。実際に人の社会的評価を低下させる必要はなく、そのおそれさえあれば「事実」を摘示したことにあたるのです。
人の名誉の毀損
人の名誉とは、人が社会から受ける評価、価値のことです。
被害者自身の評価ではなく、あくまで社会的な評価という意味です。毀損とは、人の社会的評価又は価値を低下させるおそれのある状態にすることを指します。
人の名誉を毀損することの認識(故意)
名誉毀損罪は犯罪事実の認識がなければ成立しない故意犯です。名誉毀損罪の故意とは、
この発言、情報を発信すれば人の社会的評価又は価値が低下するかもしれない、低下するだろう
という認識のことです。もっとも、通常は、このような認識を明確にもった上で何らかの発言、情報を発信する人は稀でしょう。実際には、発言、情報を発信した動機、経緯、被害者との関係性、情報の内容などから、人の社会的評価又は価値を低下させる行為をしたと認められる場合は名誉毀損罪の故意ありと判断されます。「人の社会的評価を害してやろう」などという積極的な意図までは必要ありません。また、行為者が摘示した事実を嘘だと認識していた場合はもちろん、真実だと認識していた場合でも名誉毀損の故意ありと判断されます。
名誉毀損罪の特例(非成立要件)
しかし、ここが法律のややこしいところではあるのですが、前述した名誉毀損罪の構成要件を満たした場合でも、名誉毀損罪が成立しない場合があります。刑法230条の2には特例条項が以下のように定められています。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
引用元―刑法|条文|法令リード
非常に分かりにくいんですが、構成要件を満たしている場合でも
- 事実の公共性
- 公益目的
- 真実の証明
という3つの要件を満たせば名誉毀損罪は成立しない(罰しない)としています。なお、本来であれば犯罪の成立要件を証明する責任(挙証責任)は検察官にあるところ、上記3つを証明する責任は被告人(今回は立花氏)側にあると解されています。したがって、被告人側が上記3つの要件の証明に失敗した場合は、原則に戻って名誉毀損罪で処罰されるということになります。
本記事では、名誉毀損罪について調べてみましたが構成要件の範囲が広く、噂話が好きな人は要注意ですね。故意に他人を貶めようとするような発言・発信をしなければ大丈夫だとは思うのですが、不用意な発言をすると突然訴えられるかも知れません。次の記事では今回の名誉毀損罪と似て非なる「侮辱罪」について調べてみようと思います。
広告
 | 価格:7569円 |



コメント